農場づくり 放牧養豚の罠/土・牛・微生物 D・モンゴメリー著/放牧を見直す
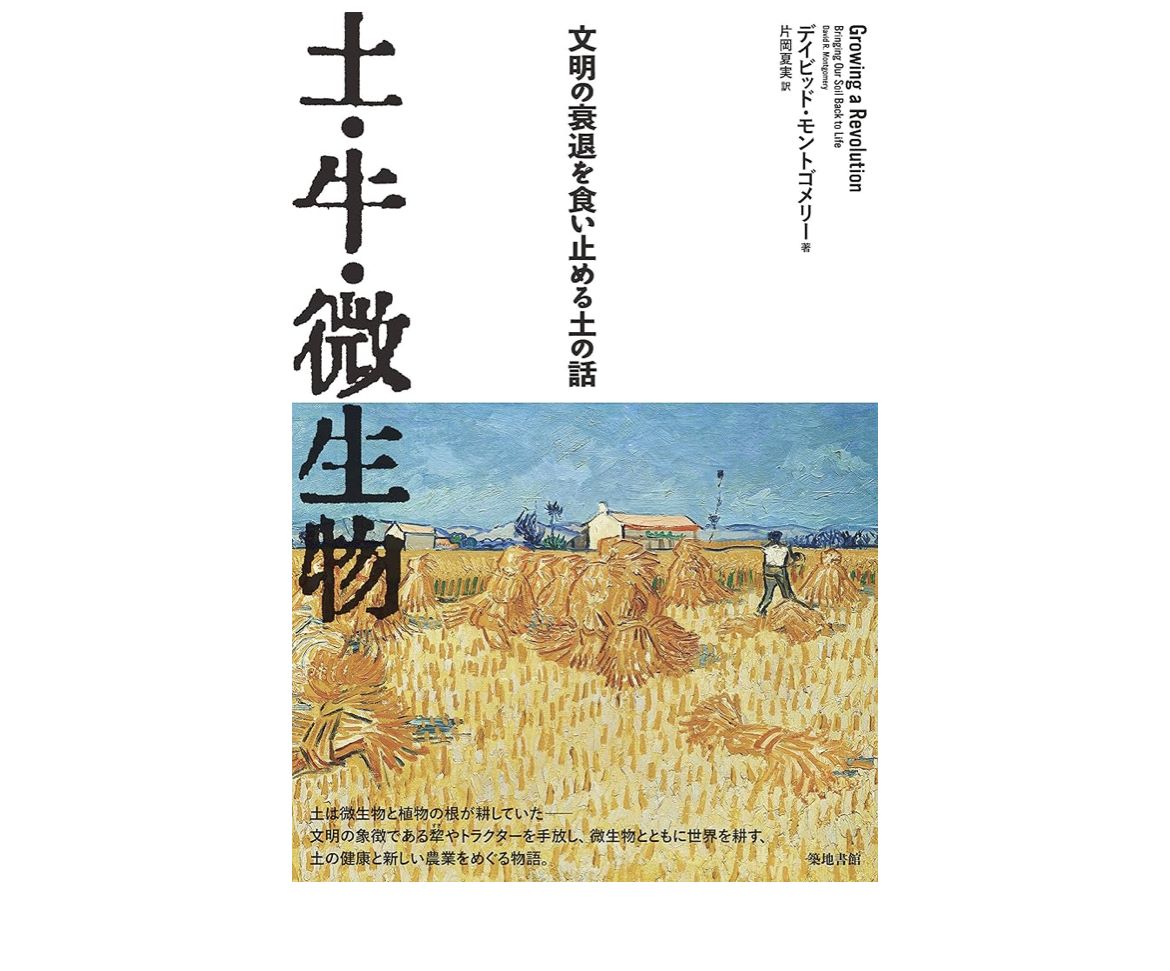
春がだんだん近づいて来ています。
待ち遠しく
そわそわ
心がざわつく季節です。
子豚の出産
肥育豚の受け入れ
豚や羊
ニワトリたちを
放牧させてやる季節
草が生い茂るまで
まだあと2ヶ月以上かかるでしょうか
地面の中はまだ
凍土で
スコップは入らない状態です。
岩のように固く
修理したい柵やゲートなど
まだ凍り付いたまま
雪が解け
ぬかるんだ地面が乾き始め
草が芽吹き
凍土も溶け始めるころ
5月を過ぎて
ようやくここ阿寒の春を迎えます。
それでも確実に
冬が終わりを告げています。
雪が解けて
少し歩きやすくなったら
鹿撃ちに行きたいです。
数日前、トラクターで除雪をしていると
鹿の毛束が
雪の中に落ちていました。
毛が抜け生え変わる時期なんですね
早いなー
今年は革を取れなかったので残念です
冬毛が毛皮には良いので
また来年の楽しみにしておきます。
もしかしたら拾い角が見つかるかも
春雪解け後、少し散策してみます。
鹿は毎年
春に角が落ち
生え変わります。
を何度も読み返しています。
足元の微生物をどのように扱うか?
世界の農業が持続可能で、農民が富み
温暖化対策になるのか?
アメリカやアフリカで行われている
先進的な不耕起栽培
輪作
被覆植物
の3つを活用した
環境保全型農業のあり方。
古くて新しい農業のあり方。
心を惹かれます。
とても面白い本です。
オススメです。
豚を飼うものとして
豚が放牧に適しておらず
豚舎での集約的な舎飼いが一般的になった理由も
放牧養豚をしていると理解できます。
豚たちは地面を掘り起こし
草木の根を食べ
その周りに生息する虫や微生物を食べ
小石を舐めてミネラルを吸収し
ブルトーザーのごとく放牧地を天地返ししていきます。
地表十数センチの何年も堆積した「土」
微生物などが生息する
有機物層は2週間でなくなり
その下の砂利、瓦礫、粘土層が剝き出しになり地面を覆います。
そのまま何年も
同じ場所で放牧すると
放牧地が荒れ泥濘化するか砂漠化し
土は死んでいきます。
土地が荒れるので
農家は放牧地や畑地が荒れるのを避け
豚舎を作り
効率性から徐々に
その中のみで飼うようになっていったのではないでしょうか
人が豚を飼う知恵なのだと今では思います。
牛や羊は草をはみ根まで食べることはありません。
豚たちは表土ごと全てをたべてしまう。
とても広い土地で本当に自由にいくら食べてもひっくり返しても
自然が回復する時間を与えられるほど大きな地域だと良いのでしょうが
日本の狭い国土で豚を何万頭も放牧できる地域はありません。
豚舎で工業化し
管理する。
国土にあった豚の生産手段なのです。
豚は放牧するにあたり非常に難しい家畜です。
多くの放牧養豚農家を見ていますが
とてもマイノリティーなのが理解できます。
非効率で土地に合っていない。
全ての農場は
ほぼ、砂漠化した状態か泥濘した状態となっています。
私の農場も例外ではありません。
表層土が荒らされ
めくられ
剥き出しになった地表は
雨水は浸透せず
地表に残ります。
また山からの染み出た水があふれ出て
地面で吸収できず地表に浮き出てきます。
泥や砂の上に水がたまり
豚たちが攪拌する。
泥濘化した地表はいつまでたっても水が引かない状態で
特に雪解けの春
降水量が多い夏の時期
パドック内に入ると足が抜けないぐらいに泥濘してしまいます。
昨年まで
対策として
明渠を各所に堀り
水はけの改善を図ってきましたが
春、雪解けの時期
明渠は豚たちに攪拌され、崩れ
ほぼ機能しない状態となっています。
春になり水が引いて少し固まったころ
ユンボで掘削して明渠づくりをする。
こうして水はけについては、少し改善されますが
根本解決には至りません。
土地が荒れ
「土」が無い状態は変わらないのです。
私の農場の根本課題の一つです。
土を回復させつつ
豚の放牧をする。
これは相反する行為で矛盾します。
近代農業のありかたについて
D・モンゴメリーは
近代慣行農業は
土を耕起することが常識となっています。
土を耕起し空気層に触れさせ有機物の分解を促進すると。
しかし
土を耕起することにより
土壌が壊され、流出する原因となり
剥き出しになった表土は風で流され
水で浸食を受ける。
対策として
大型トラクターのプラウでの耕起をやめる。
不耕起が原則で
地表面を植物でカバーすることを絶対条件としています。
また
連作することにより
土中有機物と微生物や細菌層に悪影響を及ぼし
化学肥料はすべてを吸収せず
半分以上が河川や海へ流れ出て
海洋生物や人間の飲み水にも悪影響を及びしている。
出来るだけ多くの生産物を輪作することにより
土中栄養素を保ち
悪性の細菌や微生物や昆虫が生存できない環境を作為する。
①不耕起
②被覆植物
③出来るだけ多くの輪作
この3つをすべて実行することで
地表が回復し
生産性が増え
化学肥料などの投入量を低減できる。
としています。
この原則を理解したうえで
放牧養豚に活用することはできないのか?
①の耕起をやめる。
に関して、豚たちを放牧すると「耕起」してしまいます。
ある農家は「昔は豚に鼻輪をして掘り起こしできないようにしていた。」
と言っていましたが、それはやりたくありません。
豚の耕起は本能でそれをコントロールすることはできません。
彼らにとって「耕起」を制限されることは大変なストレスです。
そこで
対策として、放牧しない時期を設ける。
放牧地をローテーションする。
が考えられます。
よくアメリカのHomestead(家族農場規模の小規模農場)で
見かけるのはネットになった電気柵を
放牧地に展開し
放牧地の状態を見ながら
ネットを移動していく要領です。
しかし
家族規模で豚が数頭の場合はこれでもできますが
商用で数十頭から数百頭になると難しくなります。
ネット電気柵の展開は見た目より非常に難しく
大きな平らな放牧地が主たる対象で
山間部や錯雑した地域での使用は
枝などや地面の凹凸により
ネットを展開するのに時間と労力がかかります。
また、コストも50m/約50,000円と安くはありません。
放牧地のローテーションを考えるにあたって
まず一つ目の課題は
牧柵の素材をいかにして労働力、経済面から効率よく放牧をするかです。
そして二つ目は放牧するための土地をいかに確保するか。
三つ目は何頭単位でGPを作りローテーションするか。
そこから
ローテーション計画、放牧計画が必要になります。
結論から
今年の放牧ローテーション計画は
現在の放牧地2か所2ヘクタール弱程度の土地を使い
それぞれ15頭をグルーピングして
一箇所につき4~6か所に区分してそれぞれ一ヵ月をめどに
ローテーションしていきます。
ローテーションの時期は土地の状態を見ながら
早めたり
遅らせたり
放牧地の牧柵素材は電気柵のみで
その都度、移動前に電気柵を張り直し
そこに誘導して放牧する。
草が生えそろう5月半ばから11月末までの間です。
約半年間
一度放牧した地域は4ヶ月以上、最長半年間は未使用になる予定です。
この土地の休養間に新しい草が芽吹きます。
新しい草がある程度育ったら
そこに野菜など、何かしらの種をまく予定です。
種をばらまきした後
生育した草を刈ります。
天然マルチの完成です。
天然マルチの下で微生物が有機物を猛烈な勢いで分解し
分解後の栄養素を野菜の種が発芽したころ吸収し大きく育つ。
豚たちが戻ってくる前に収穫し
残ったものは豚たちが食べられる。
このような循環をイメージし放牧する予定です。
問題点の一つ目は
約15頭のグルーピングで豚たちのヒエラルキーが
うまく機能するか?ストレスはかからないか?
地域が狭いところに密集する形となりますのでここが心配です。
併せて、場所の制約上、
母豚、子豚、父親を同一のグループに含ませなければ
ならない為、そこも心配です。
二つ目は
シェルターと水の確保です。
現在のシェルターは移動できるように小型に作っていますが
果たしてうまく錯雑した中を移動できるか?
水は湧水で各パドックに配線していますが
移動させるとなると使用できなくなります。
その為、水場の確保が必要です。
ウオータージャグをもう一つ準備する必要があります。
これもトラクターでの運搬ができない地域が出てきますので
人力での運搬となります。
夏場は数日に一回は水を補充する必要がある為
労力上、負担がかかります。
D・モントゴメリーによると
牛の放牧も高密度での放牧が適しているといいます。
なぜか?
牛は広い地域で自由に放牧すると
美味しい草から食べ始めます
好みでない草は残り
まばらな状態となります。
残った好みでない草が種子をおとし
次の年に増える
これを繰り返すと、放牧地全体が食べられない草で
一杯になってしまいます。
これを防ぐには?
広い土地を区切って
そこに牛を高密度で放牧する。
これにより、競争が生まれ
牛は草を選り好みできなくなる。
兄弟が沢山いる家庭の食事と同じだと言います。
早く食べないと、食べるものがなくなってしまう。
そのようにして均等に食べられた放牧地から
次の放牧地へ移動させていく。
それもランダムに規則正しく移動することなく。
こうすることで寄生虫や伝染病の連鎖を断つ効果もあります。
次の年まで牛が来ない
また牛が来るかどうかもわからない為
寄生虫の繁殖が行われないというのです。
土地も十分な回復期間があり
有用な微生物が豊富な有機物を分解する。
こうしてまた牧草が青々と生い茂る。
北海道の農業において
放牧地を地盤改良と称して
機械で全面的に広範囲の土地を天地返しをして排水を改善し
空気を混入して有機物の分解を促進させる事業が
頻繁に行われています。
公的補助を得て土木業者と一体になり定期的に行うことが良し
とされているそうです。
しかし
不耕起
被覆作物
多様な連作
の考え方で「土」づくりをすることから考えると
微生物層を破壊し
良質な土壌を壊す行為に見えます。
ご自身の著書の中で科学的に検証した結果
地盤改良が無駄であり土壌破壊をしていることを
指摘されています。
さて
牛と豚は性質が違うので
何とも言えないですが
今年は高密度で放牧する方法を利用して実験してみたいと思います。
